対応!
詳細なご相談内容がある方
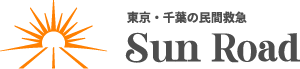
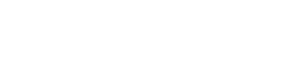
対応!
詳細なご相談内容がある方

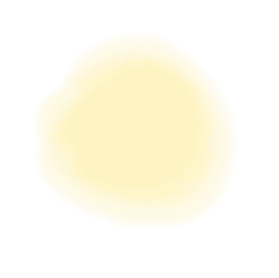
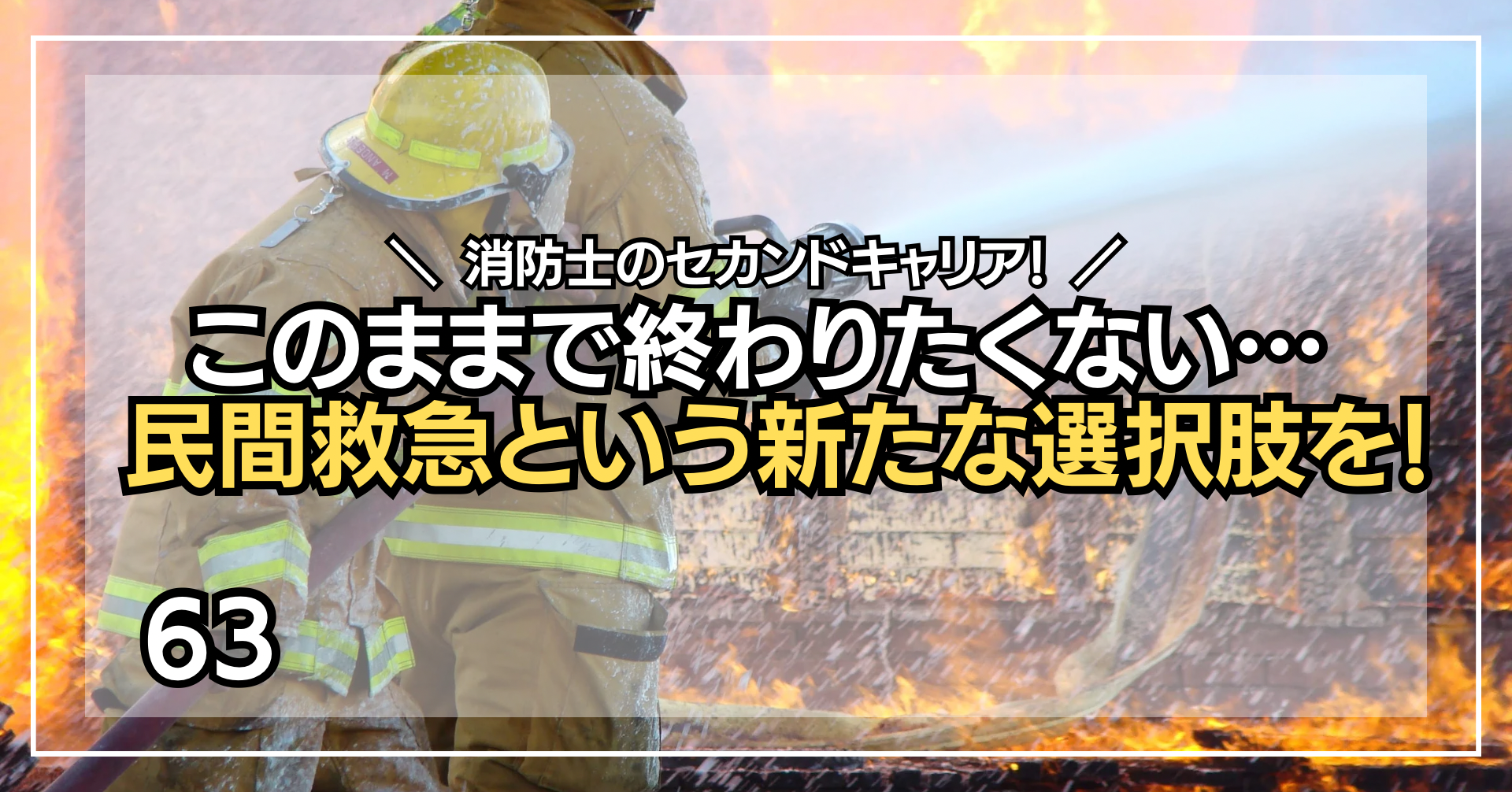
「このまま定年まで勤め上げて、本当に満足できるだろうか?」
「退職後、自分の経験を活かして何かできないか…?」
こうした想いを抱える消防士・救命士の方は年々増えています。
その中で、近年注目されているのが「民間救急」という働き方です。
公務員時代に培ったスキルや信頼性を活かしながら、地域社会に貢献できる仕事として、第二のキャリアに選ぶ人が増加中です。
ただし、民間救急は「救急車の代わり」ではなく、届け出・装備・連携体制などが求められる専門事業。
興味はあっても、
…という声も多く聞かれます。
このコラムでは、消防職13年の経験を持つ筆者が、
民間救急の開業までの流れ・必要な設備・収益構造などを実例ベースで丁寧に解説します。
独立開業という選択肢を現実的に考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
民間救急とは、病気やけがなどで移動が必要な方に対し、専用車両と医療スタッフが付き添って搬送するサービスです。
119番で呼ぶ救急車とは異なり、緊急性は低いが医療的なサポートが必要な搬送を担っています。
最近では、病院から病院、病院から施設、自宅から病院など、さまざまな搬送ニーズが増えており、公務員経験者のセカンドキャリアとしても注目されています。
消防職や救命士としての経験は、まさにこの仕事にぴったり。現場理解・判断力・ご家族への説明力など、多くのスキルがそのまま活かせるため、地域で安心される事業としても期待されています。
民間救急を開業するには、「ただ車両を用意すればよい」というわけではありません。
事業として運営するには、各自治体の基準を満たす必要があり、特に以下の3点が大きなポイントになります。
自治体ごとに手続きや認定条件に違いがあるため、開業を考えたらまず「所轄の消防署」に相談するのが第一歩です。
また、保健所や医療機関との連携体制も、地域に根ざした信頼づくりには欠かせません。
民間救急は、「患者搬送」という公共性の高い事業でありながら、しっかりとした収益モデルが存在します。
収入源の多くは「搬送料金」ですが、それだけではありません。実際には以下のような複数の収益ポイントが存在します。
特に長距離搬送や精神科搬送は単価が高く、1件あたり5万〜15万円以上の収益となるケースも少なくありません。
また、地域によっては同業他社が少なく、競合優位性を築きやすいのもこの業界の特徴です。
民間救急を開業するまでには、いくつかのステップを段階的に踏んでいく必要があります。
設備や車両、人員体制を整えるだけでなく、所轄の消防や保健所との調整も欠かせません。
下記の表は、実際にSun Roadでも採用している「開業スケジュール」の一例です。
おおよその目安として、準備から開業までに必要な期間は「3ヶ月〜6ヶ月程度」。
行政手続きに時間がかかることもあるため、早めの準備がおすすめです。
| 時期の目安 | やること | ポイント・備考 |
|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 市場調査・所轄消防に相談 | 自治体ごとに条件が異なるため、早めに相談を |
| 2ヶ月目 | 車両・装備の準備、人材確保 | 車両選定は地域の道路環境にも配慮する |
| 3ヶ月目 | 搬送事業者認定の申請 | 書類審査・実地確認がある場合あり |
| 4ヶ月目〜 | 営業開始・地域医療機関との連携 | 搬送実績が積み上がると紹介が増えていく |
民間救急の開業を考える方にとって、ありがちな「落とし穴」はあらかじめ知っておくことが重要です。
多くの失敗は「準備不足」「制度理解の甘さ」「マーケティング軽視」に起因しています。
逆に言えば、これらを事前に把握し、対策しておけばスムーズな立ち上げが可能です。
以下に、よくある失敗パターンとその回避ポイントをチェックリスト形式でまとめました。
「民間救急を始めたいけど、一人で全てを準備するのは不安…」
そんな声に応えるために、Sun Roadでは元消防士・救命士による「民間救急の開業支援サービス」を提供しています。
単なるマニュアル提供ではなく、現場を熟知した実務経験者が、あなたの地域・状況に合わせて具体的な支援を行います。
特に以下のような内容をサポートしており、すでに開業を成功させたパートナーも複数存在します。
民間救急の開業は、決して簡単ではありませんが、元消防士や救命士にとっては非常に相性の良い事業です。
これらを強みにできるからこそ、地域の搬送ニーズに応えながら、しっかりと収益化も目指すことができます。
「第二のキャリア」として、または「地域貢献をしたい」という想いの延長として、
民間救急という選択肢をぜひ前向きに検討してみてください。
Sun Roadでは、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
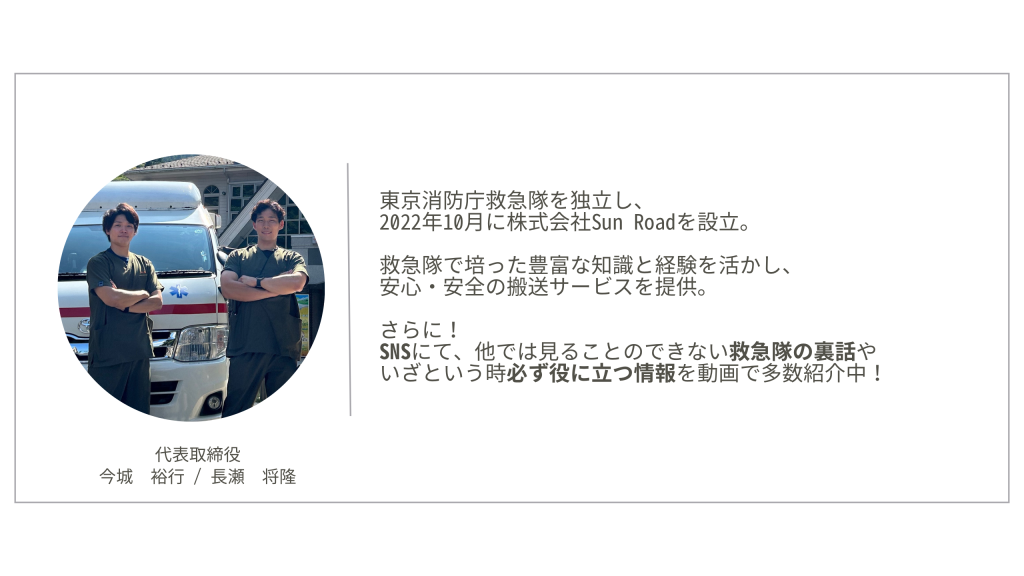
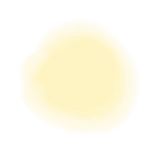
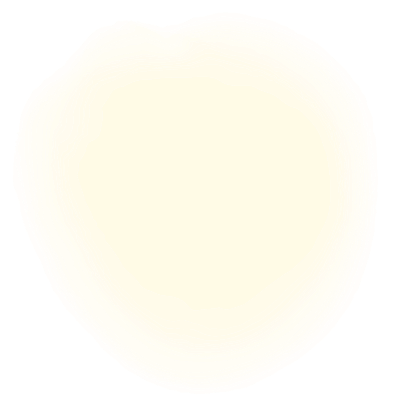

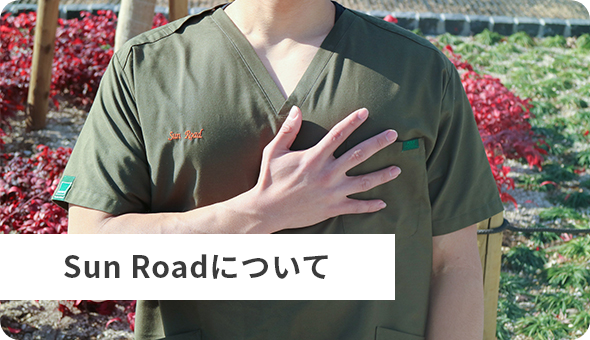

精神疾患搬送や長距離搬送など、患者様の状態に応じた搬送のご予約・ご相談を承ります。
詳細なことが決定していない場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
お急ぎの方は、お電話でのご予約も可能です。
電話が難しい方はこちら